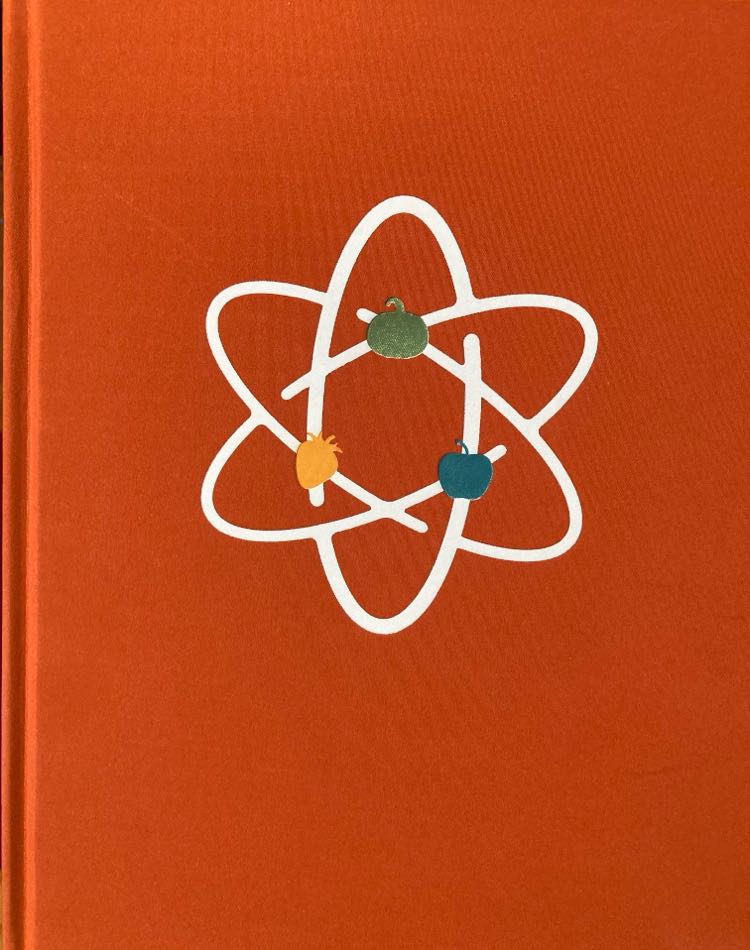
昨年Vanishing Incから出たジョシュアジェイの本で、オリジナルのParticle Systemとそれを使ったトリックが解説されています。
オリジナルのスタックというのは色々ありまして、当サイトで扱っただけでもタマリッツスタック、アロンソンスタック、ダオルティススタック、レッドフォードスタック、アラゴンスタック、あとDrew Backenstossのスタックの本とかもありましたね。
メモライズドデック単体のトリックであればスタックはなんでもいいんですが、これとこれやりたい!みたいなのがあってモチベーションが高まってくるとオリジナルのスタックでというとこに行き着くわけです。
よくメモライズドデック覚えるなら何がいいかみたいな話がありますけど、結局は何をやりたいかというところがあって、研究されてるしスタック依存トリックの数が多いタマリッツスタックが良いのは良いんですが、別にそこにやりたいことがないなら色々応用の効くサイクリックスタックやステイスタックを覚えてしまった方が良い説もあったりします。
ちなみにこの本にはスタック依存トリックとそうでないトリックがどっちも解説されていて、メモライズドデックのトリックは普通に出来が良いし、スタック依存の方は別に配列覚えてなくても出来るようなトリックが多いので、これからメモライズドデックを頑張るという人でも読みやすい内容です。
もちろんメモライズドデックを嗜んでいれば読めば即戦力になるような良いトリックも解説されているし、何かメモライズドデックを使ってる人をParticle Systemに乗り換えさせるような文があったりして、別のスタックに慣れてる人もターゲット層になっています。
というわけでParticle Systemはどういう特性があってどういうことができるのかというのが最初のチャプターにまとめられているのでそこの紹介からいきましょう。
Part I: The Particle System Explained
まずはスタックの作り方とParticle Systemとはなんぞやということが解説されています。
いろんな良い所がありまして、ニューデックオーダーから簡単に作れるとかニューデックオーダーのエンディングができるとかAとKが扱いやすい場所にあるとかロイヤルフラッシュを配れるとか、この後で解説される手順の豊富さでも分かるんですがなんやかんやとメリットが盛りだくさん。
微妙なところとしてはよく見ると法則性というかあんまバラバラじゃないのがわかってしまう点です。
そこについてはジョシュアジェイも自覚しており、カバーする方法も解説されていますし、そもそもバラバラに見えることってそんなに重要かね?というような事も書いてます。
個人的にこれは結構同意できる感じでした。パッと見わかるわけじゃないし、その他のメリットが上回っているのであれば十分このシステムを使う理由になるでしょう。
さて、Particle Systemは単なるスタックでなく色々と工夫してシステムになっているもので、その解説もここでされています。よりプロフェッショナルな現場で使いやすい工夫です。逆に言うといわゆるマニア的な視線では敬遠しがちなあれこれ。
これはレッドフォードの本でも似たような解説がありましたが、メモライズドデックをより強力にするものなので、既存のメモライズドデックを使ってる人にも参考になる内容になってます。
あとフォールスシャッフルとかスタックの扱いについてのもろもろについてもここで解説されてます。フォールスシャッフルは既存技法のちょっとしたアレンジと言った感じで、ラフに見えるものが多くていくつか取り入れてみたくなりました。
さて、ここからは具体的にParticle Systemを使ってどんなトリックが出来るのかという話です。
Part II: Close-up Magic
まずはクロースアップのトリックから。
Remember to Be Honest
2枚のKが2枚のAに変化するトリック。
まあジャブみたいな感じですが、セリフは良いし観客の手の中で起こる現象なのでオープニングにはとても良いでしょう。
Memorized X-Ray
演者はずっと後ろ向きのまま観客が真ん中で表向きにしたカードと位置を当てます。
実はリスクもあるのですが、Particle Systemのおかげでかなり安定して出来るようになっているし、もし事故っても最終的に残念なことにならない構成が良い感じです。
Invisible Touch
観客がカットした枚数を当てる、観客が言った枚数をカットする、カードアクロスの三段構成。
2段目の手法はParticle Systemだからこそという安定感があり非常に実用的です。
カードアクロスに繋げる構成は見た目も面白いしメソッドもとても気に入りました。
Back In Time
時間が戻る演出のトライアンフ。
これは別のところでも解説されてる通りスタックとかあんま関係ないです。
もちろんリセットも即。
Presentation for Thought-of Card
Thought-of Cardやコールカードの現象に関する考察です。
非常に強力な現象であるが故の注意点やよりインパクトが強まる見せ方について書かれています。
また、Particle Systemとの相性の良さについても触れられており、これは既存のスタックで工夫しても行ける話なのでメモライズドデックユーザーなら参考になる話でしょう。
The Imaginary Card Trick
観客はカードを引いたふりをするだけなのですが、観客が言ったカードが突然現れます。
これはめちゃくちゃかっこいい。観客の手に現れたように見せるバリエーションが特に良かったです。
Sequenced
観客がパケットをシャッフルしますが完全にメイト一致します。
これもとても良かった。Particle Systemのクライマックスに十分でしょう。
初期状態から少しスタックをいじる必要があるのですが、その部分のセリフとかも考えられています。
The Curious Incident
観客がシャッフルしたデックの順序を暗記してしまい、最後は観客が1枚抜き出したカードも当てます。
シャッフルのさせ方と関連技法はとても参考になりました。プレゼンテーションも面白く、説得力があるトリックです。
実はバラバラに見えないParticle Systemには向いてないトリックなのですが、どう演じれば良いかについても解説があります。
Part III: The Parlor Show
パーラー向けのトリックが解説されたチャプター。
Fooling About
トリック自体は選んだカードを取り出す的なものなのですが、主な目的がデックスイッチでとても巧妙なやり方で感心しました。
トリックの中でデックスイッチするのはアロンソンのあれ的なあれです。
Matching the Cards
Particle Systemのメリットの一つ、Matching the Cardsができる!
フォースの仕方から何から地味にハンドリングも凝っていて良い手順です。
Memorized Multiple Selection
マルチプルセレクションのリベレーション手順。
これスタックはあんま関係ないんですけど、出し方がいちいち洒落てて後半どんどん盛り上がる良い感じのルーティンでした。
Weighing Across
Weighing the Cardsとカードアクロスの組み合わせ。
これは結構前からジョシュアジェイがやってるやつですね。
Weighing the Cardsの演出がとてもとても面白くて、カードアクロスへの繋ぎもとても綺麗。カードアクロスのカードを数えるだけのパートが現象になってるので退屈な部分がありません。
手伝ってもらう観客を1人にしたライトバージョンも解説されています。
One Card Poker
タンタライザーで、終わったらニューデックオーダーになります。そのために少し特殊な配り方をするのですが、その部分も上手く演出に絡めていて退屈しないようになってます。
また、タンタライザーにサプライズを、というのもテーマになっていて、ちょっとしたアイデアが凄く良い味出してるトリックです。
このトリックの後にニューデックオーダーを使えますが、これがオチでも良いと思える面白い見せ方です。
Fireworks Finale
ニューデックオーダーで行うスートアピアランス。
全部が解説されてるわけではありませんが色んな技法が紹介されています。おしゃれ。
Part IV: Miscellaneous Effects
色々。
Think as I Think
観客と演者でお互いにカードを言ってそれをお互いに見つけるという手順。
これもジョシュアジェイが結構昔からやってるルーティンで、これ系の中では手続きがとてもシンプルで動機もしっかりしたトリックです。
ただ、デックを半分に分けるのですが、カードは自由に言うのに半分の中にそのカードが入ってるとは限らないみたいなところは消化しきれてない気はします。
Particle Pair
観客が指定したペア(赤の10とか黒のJとかの2枚)を探すトリック。
Particle Systemならではの作品で、軽い感じのトリックですがプレゼンテーションもしっかりしておりリセットも楽なのでParticle System使うなら演じたい。
The No-Card Index
演者と観客がそれぞれデックから1枚ずつ選び、それが一致してる確率を黒板を使って説明します。もちろんカードは一致していて、説明で使った黒板をひっくり返すと選んだカードの名前が出てきます。
カードを使わないインデックスという面白いアプローチで面白い現象の一作。当然フォースではありません。
The Same, But Different
観客が引くカードをあらかじめ言い当てる、それも3枚も!というトリック。
Harapan Ongの “Direct Triple Prediction”のバリエーションで、Particle Systemを使うことでより演じやすくなっています。
Catch This
Pit Hartlingの “Catch Me If You Can” のバリエーションで、Particle Systemのおかげでサンドイッチカードを綺麗に出来る!というもの。
手続き自体も違っており、観客が指定するのはサンドイッチカードの方。ということはセレクトカードはなんやらせなあかんのですが、ここはメモライズドデックを使ったトリックとして好み分かれるところでしょうか。
Distilled
観客に海と山のどっちが好きか、みたいな質問をしていき対応するパケットを残してデックをどんどん減らしていき、最後に残った1枚が観客のカードというトリックです。
手法は地に足のついた感じで、最後の1枚の処理もなかなか良いです。
The Magic Square
Particle Systemが魔法陣に使えるという話。
Triple Pocket
観客3人に1枚ずつカードをポケットに入れてもらい全部当てます。
実際はそうではないのですが演者がほとんどデックに触れてない印象を与えるトリックで、選ばせ方も少しずつ変えてどんどん盛り上がる感じのトリックです。
原理もメモライズドデックならではという感じで面白い。
Part V: The Memorized Filter
既存のトリックがParticle Systemで演じられる、もしくはParticle Systemによってより強化されるような手順が載ってるチャプター。
Flush Brush
Dong Conn の “Flush Brush”、これもParticle Systemで上手いことできます。
あのマットの裏のゴム使ってロイヤルフラッシュをプロダクションしていくやつです。
Chaos
Pit Hartling の “Chaos” をParticle Systemでやる方法。
スタートの状態が違うのでカードを選ばせる手続きなども違います。原案の演出も面白いのですが、場合によってはこちらの手続きの方が自然に見える気もします。
Rubbed Away
Joel Givensのカードを消す技法、Particle Systemなら観客が指定したカードで速攻できてしまいます。
Another Bottom Feeder
ケースの中に入れた2枚のKの間に観客が言ったカードが挟まるトリック。
これはParticle Systemでなくても出来るやつで、とても良いです。単純にコールカードの現象としてではなく、想像力を働かせる演出も素晴らしい。
Matching Hand
観客が選んだ手札のメイトの手札を出していきます。
ギャンブルがテーマですが単純に配って見せるのではなく目に楽しい感じでプロダクションしていく見せ方。
Quicker Dead
観客がポケットに入れたカードのメイトカードを取り出します。
デックはケースにしまってポケットに入れた状態にしますが、瞬時に取り出すことができます。
Particle Systemならとても手軽にこれが出来る。
Moe’s Memorized Move-a-Card
Move-a-Cardもめちゃくちゃ簡単にできます。
まああんまり広げた状態で見せれないので相性良いかは微妙なところでもありますが。
Part VI: The Gambling Show
ギャンブルを扱ったチャプター。
Aces and Kings Production
ブラックジャックのセリフがついたAとKのプロダクションです。
スタックがとても便利な感じになってるので、プロダクション部分は割と自由になんでも出来ます。
Ten Card Poker Deal
ヨナカード式の10カードポーカーディールでフェイズごとに観客に有利になるように見せる構成です。
最後はスマホで取った手札と全く同じ手札にならなければ演者の負けという演出で、手法もとても気に入りました。
Particle Systemの一部を使って演じることができ、リセットも自動的に行われる良手順。
The Particle Gambling Demo
ロイヤルフラッシュを配ったあと、マークごとにA〜Kの順で配るクライマックス手順。
ディーリングテクは必要なく、ほぼセルフワーキングで出来ます。
Epilogue
最後に2つのトリックが解説されています。
Three Act Structure
観客が言ったカードでカットします。
いくらParticle Systemでも不都合な場合というのがあるのですが、そこの解決策が良かったです。
クライマックスは観客の誕生日の枚数目からそのカードが出てくるという現象になってます。現象だけだとちょっと歪曲的な感じはありますが三幕構成のストーリーに沿ったものでクライマックス感があります。
Your Turn
観客が言ったカードが観客がカットした場所から出てきます。
チャレンジングなプロットを十分実用的な範囲で実現しています。Particle System様様。
んなわけで、軽くではありますが全作品紹介させていただきました。
スタックを使うトリックというと大ネタ寄りのものをイメージしてしまいますが、軽いものからトリネタまでバランスよく解説されているのが良かったです。続けて演じるのが推奨されてるトリックなんかもありますので、この本だけで色んな長さのショーを組み立てることができます。
配列覚えなくて良いやつだけでも普通に良いルーティン作れるのでメモライズドデックはちょっとって人にもオススメです。
もちろんメモライズドデックを使ってる人には強く推せる一冊です。トリックだけでなくメモライズドデックをより強力にするツールの解説もあり、Particle System使わずとも自分が使ってるスタックで何が出来るか考えるヒントがたくさんあります。Particle System自体も法則性が多いので他のスタックと比較しても研究しがいがありますし、知っておけば今後マジックを学ぶ際にこれParticle Systemで出来るやんて思える機会もあるはず。
もちろんここからオリジナルスタック沼にハマるのも良いでしょう。
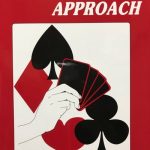
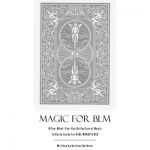



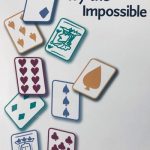
Comments
No comments yet...